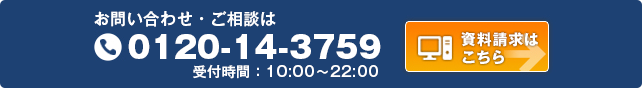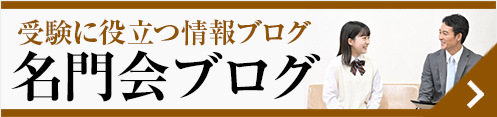名門会【 中学受験 直前対策特集 】
名門会のプロ教師による1対1【 聖光学院中対策 直前特訓 】
算数<聖光学院中学入試問題分析>
■入試傾向<学習量が得点につながる>
大問数は5題、試験時間は60分、配点は150点である。最近5年間は、【1】が小問集合、【2】以降が分野別の大問となっている。平面図形・立体図形・図形の移動、速さ・割合と比、数論分野からの出題が多い。極端な難問はないが、平易な問題もない。分析力・作業力が必要であり、学習量が問われる出題である。
■2017年出題<易化したときこそ慎重に>
2017年度は、【1】計算・速さ・立体、【2】数論・場合の数、【3】図形と比・場合の数、【4】変化のグラフ、【5】立体図形となり、図形分野からの出題がやや多かった。【2】、【3】は場合の数が絡むので慎重さは必要だが、【5】以外は標準的な難度であり取り組み易い。合格者平均点も118.0点(昨年84.7点)と大きく伸びた。
■2018年対策<王道の学習方法が合格に結びつく>
聖光の算数は、典型題にひと手間加えた出題が多い。まずは、基本となるテキストを着実に学習することが大切である。ここでは、解き方を覚えるのではなく、考え方・方針の立て方をしっかりと理解することである。その上で、過去問を利用して、問題文の正確な読み取り、的確な条件整理を身につけていくことが必要である。ありきたりではあるが、「手を抜かない」、「丁寧な学習を積み重ねること」が、聖光合格への近道である。
【 <聖光・算数>頻出テーマ 】
【1】立体図形、【2】数の性質・規則性、【3】平面図形
◆ <聖光学院中学>過去3年の入試データ
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格者最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 695名 | 645名 | 242名 | 2.7倍 | 334点/500点 |
| 2016 | 742名 | 703名 | 241名 | 2.9倍 | 318点/500点 |
| 2015 | 778名 | 734名 | 242名 | 3.0倍 | 302点/500点 |
◆ <聖光学院中学>科目別問題分析
| 科目 | 配点 | 時間 | 問題 用紙 |
解答 用紙 |
解答時間 /1問 |
問題傾向・分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 60分 | A4 | B4 | 2.1分 | 本文8000字、問題別傾向<客観70%・記述25%・知識5%>、記述問題160字 |
| 算数 | 150点 | 60分 | A4 | B4 | 2.9分 | 途中式なし、作図あり |
| 理科 | 100点 | 40分 | A4 | B4 | 1.2分 | 作図あり、問題別傾向<記号65%・用語35%・記述0%> |
| 社会 | 100点 | 40分 | A4 | B4 | 0.8分 | 問題別傾向<記号55%・用語35%・記述10%>、漢字指定あり |
聖光学院中学合格体験談
※ 過去の名門会「中学受験体験談」より抜粋、昨今の社会事情をふまえ、受験生は似顔絵・イニシャルでご紹介しています。

「難問、受験にしっかり向き合う立派な姿」
T.M君 【 合格校:聖光学院中・海城中・栄東中(東大) 】
標準的な問題を解くことはできましたが、経験不足もあって発展問題に苦戦していました。こちらが選んだ問題を解くことで、それぞれの問題に対する解法や読み取り方など、どんどん吸収していきました。塾で習わなかった解法もすぐ理解して、身につけることもできました。家庭での学習も計画的に、多めの課題もしっかり取り組めていました。難問にも受験にもしっかりと向き合い、取り組めたことは、とても立派でした。 【有川 照夫先生<談>】

「聖光の傾向に合わせ、事象の“仕組み”を重視」
H.I君 【 合格校:聖光学院中・攻玉社中・栄東中(東大) 】
聖光の理科はボーイスカウトで学ぶような日常の理科知識を質問してきます。そこで“持っている基本知識からどう理屈立てて論理的に事象の仕組みを解き明かすのか”を考えてもらいました。過去問の正解を導き出すだけではなく、選択肢一つずつの仕組みがわかるように解説して、ただの“暗記”から“思考力”へと頭を柔軟にしていきました。中学に入っても思考力を磨き続けていってほしいと思います。 【山口 知之先生<談>】

「複雑な文章題を混ぜて、問題の精読を強化」
Y.N君 【 合格校:聖光学院中・渋谷教育幕張中・東邦大東邦中・函館ラ・サール中 】
当初は問題集の解説中心でしたが、夏には自力で仕上がるようになっていましたので、その後は、立体図形や速さ、比など弱点分野中心の強化メニューを作りました。問題文の精読も課題でしたので、文章の複雑な問題を随所に散りばめるなどの工夫を施し、引っかかると大げさに指摘するなどの演出で盛り上げました。1月には集中度が高まり、出された問題を何としても解いてやろうという気迫が感じられました。 【小川 元先生<談>】